|
日本リハビリテーション医学会 |
切断のリハビリテーション |
 切断の原因 切断の原因切断の原因には、外傷、腫瘍、感染、末梢循環障害、先天性障害などの疾病があり、外傷には、産業(労働・交通災害)、政治(国際・国内紛争での兵器使用)、地震などの自然災害も含まれます。最近では人口の高齢化、糖尿病・動脈硬化症などの増加により、末梢循環障害による切断が多数を占めるようになっています。 手術 切断手術は「最後の四肢機能再建術」であり、基礎疾患・合併症の管理だけでなく四肢喪失に対する心理的なサポートが必要となることがあります。大切なことは、できるだけ、義肢を考えた切断術を行ってもらうことです。 義肢の作製まで 義肢処方・作製までの間は断端の成熟促進と切断近位の関節拘縮予防と筋力強化が重要で、四肢・体幹筋力の強化、心肺機能の強化、日常生活基本動作訓練は、義肢訓練が終了するまで続けられます。切断端の形状が安定するまでのおおよその目安は、下肢では術後6〜10週、上肢では3〜6週間で、年齢、合併症の有無、術後の断端の状況などに左右されます。残存機能とともに、年齢、職業、活動性、趣味、住居、地域の環境など含めた切断者のニーズを考慮し義肢が作製されます。 退院後の生活 就業についての職場調整,職業訓練、生活支援などのサポートが必要となることがあります。退院後1年間は断端の形状が変化することがあり、断端の問題に応じて定期的なチェックと義足の調整が必要です。 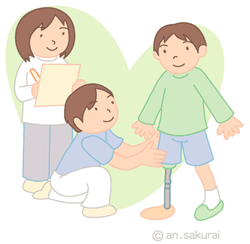 新しい義肢 新しい義肢切断者の身体に適合し、さらに切断者が暮らす社会や自然環境に適合した義肢が研究開発されています。たとえば、シリコン製内ソケットを併用した全表面荷重型下腿義足、大腿義足膝継手をマイコンで制御するインテリジェント義足があります。筋電・電動義手についても多自由度の制御、協調動作の獲得のコントロールシステムが開発されています。 今後の課題 リハビリテーションは病院の中で終了するのではなく、切断後の社会復帰をいかに図っていくかが重要です。このためには良質な情報が、だれでもどこでも受けられるようなネットワーク作りが必要です。最近は、義肢選択の相談や適合性の指導にも、インターネットなどの情報技術の応用が望まれています。 |
| 主な疾患のインデックスに戻る |